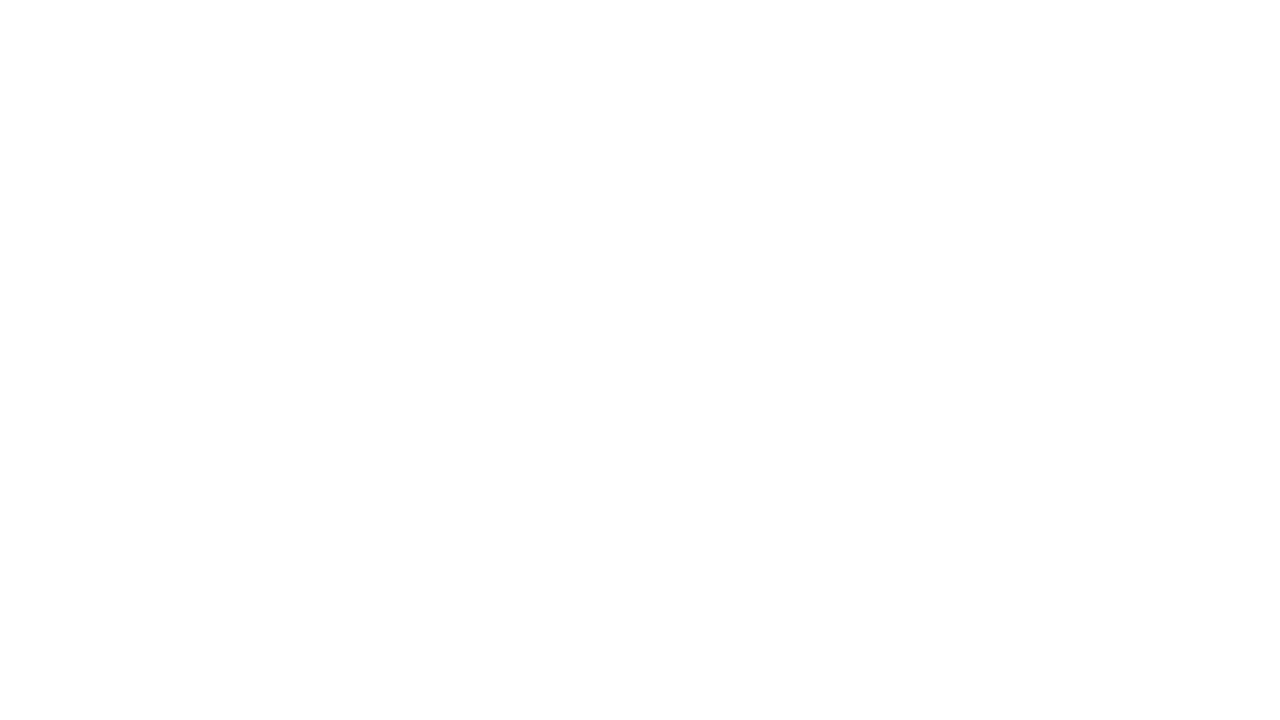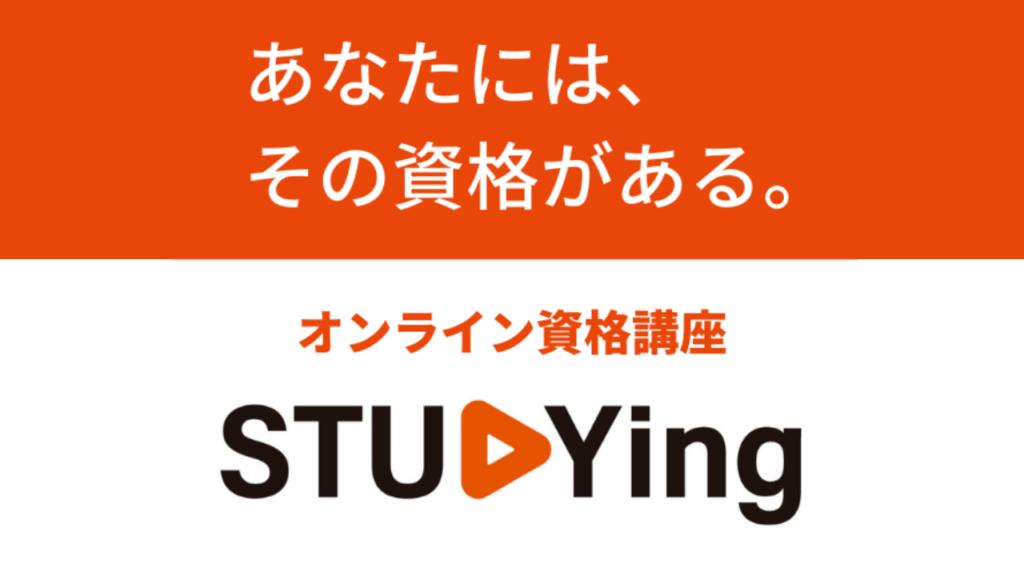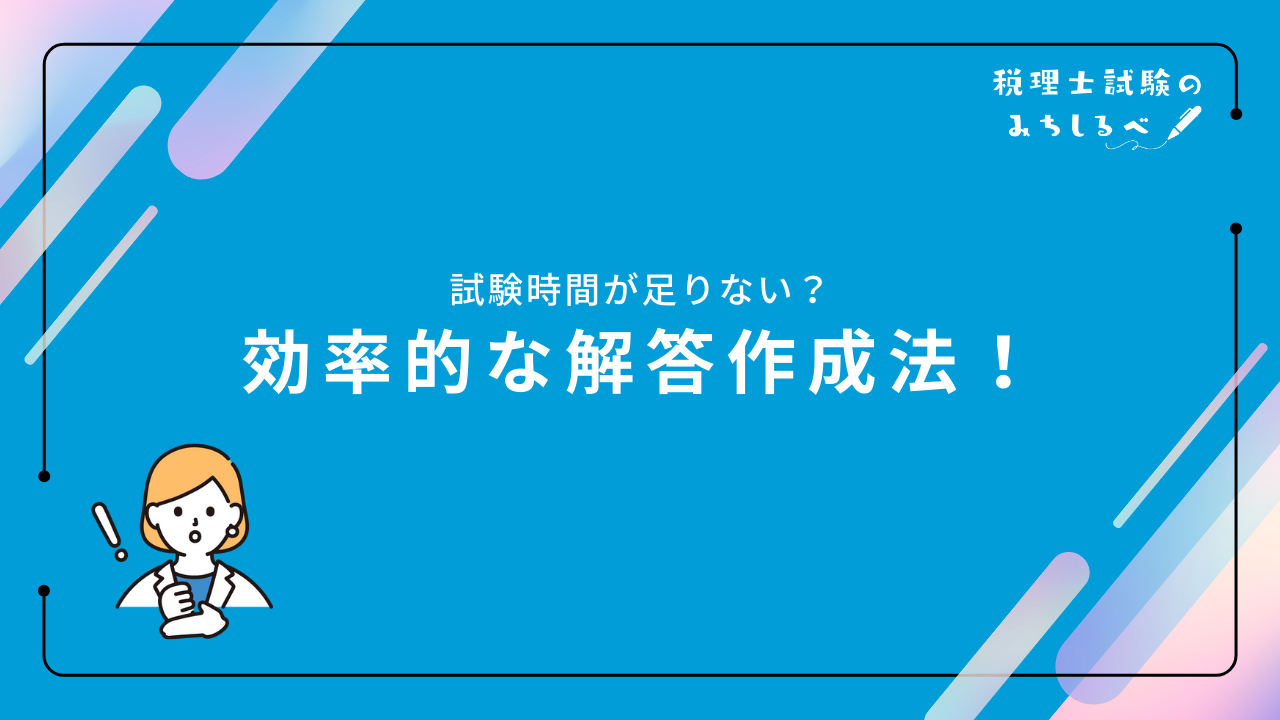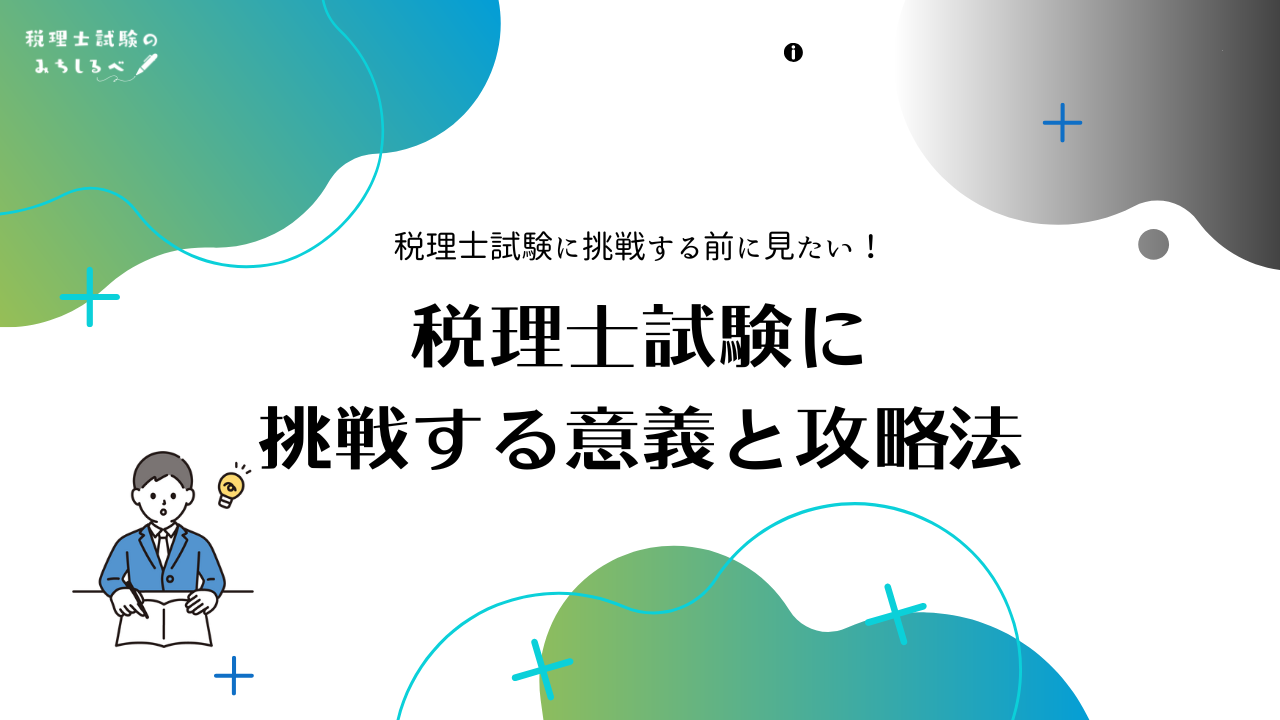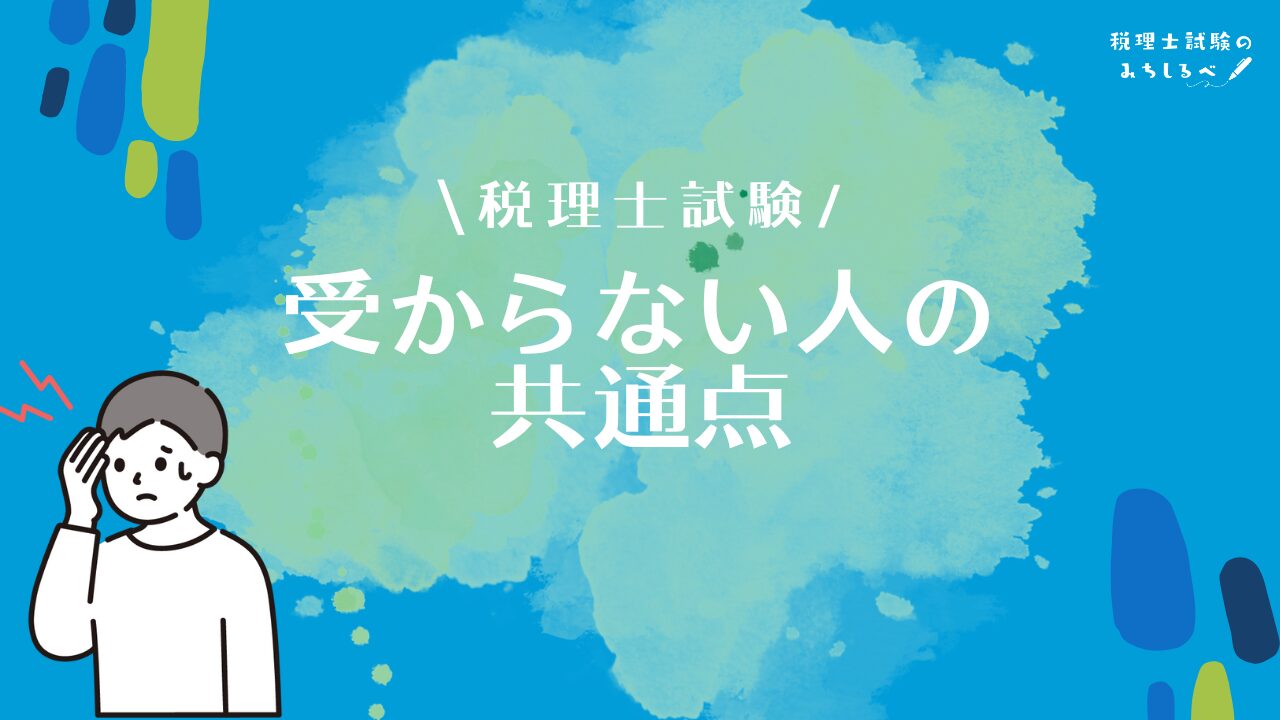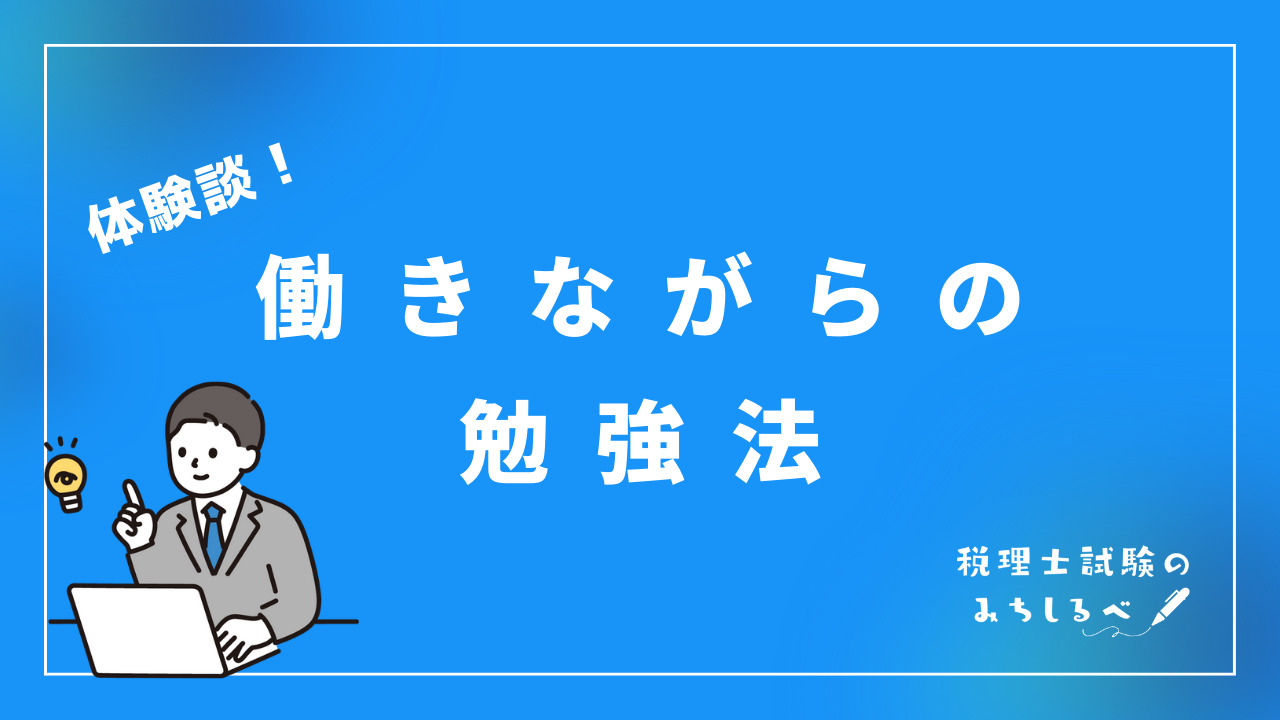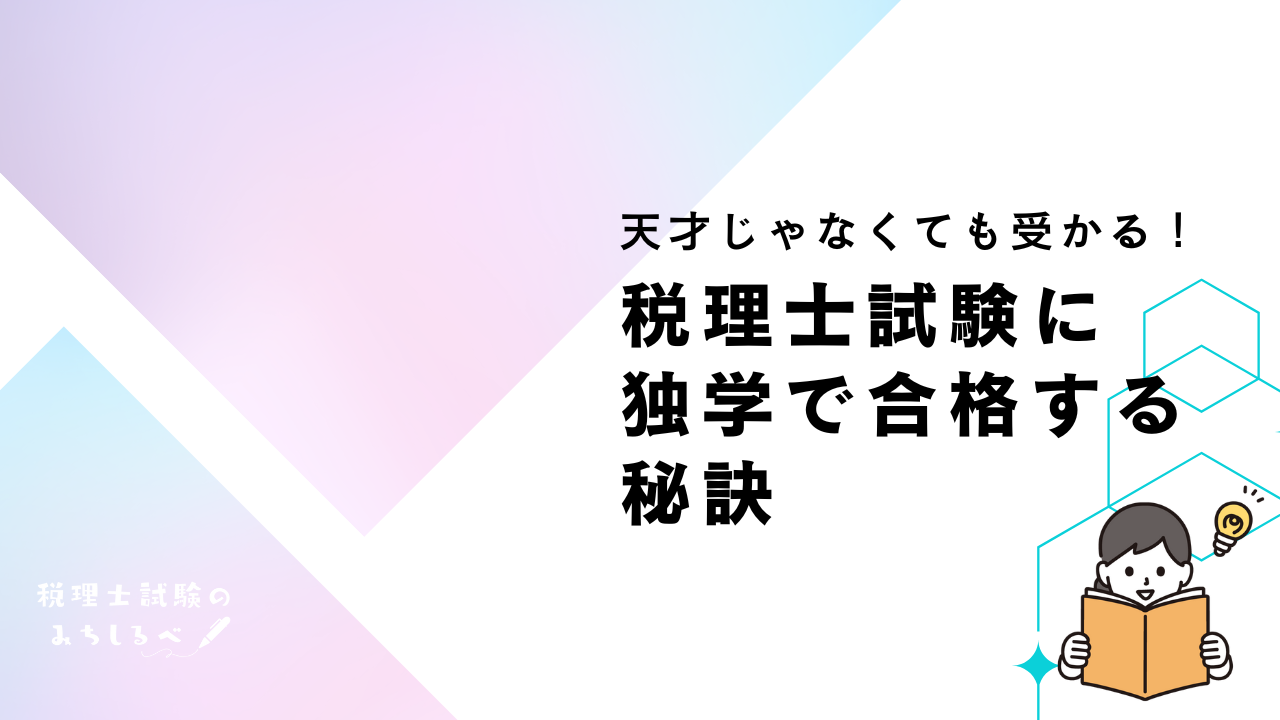仕事と両立!税理士試験に最短合格する科目の順番とは
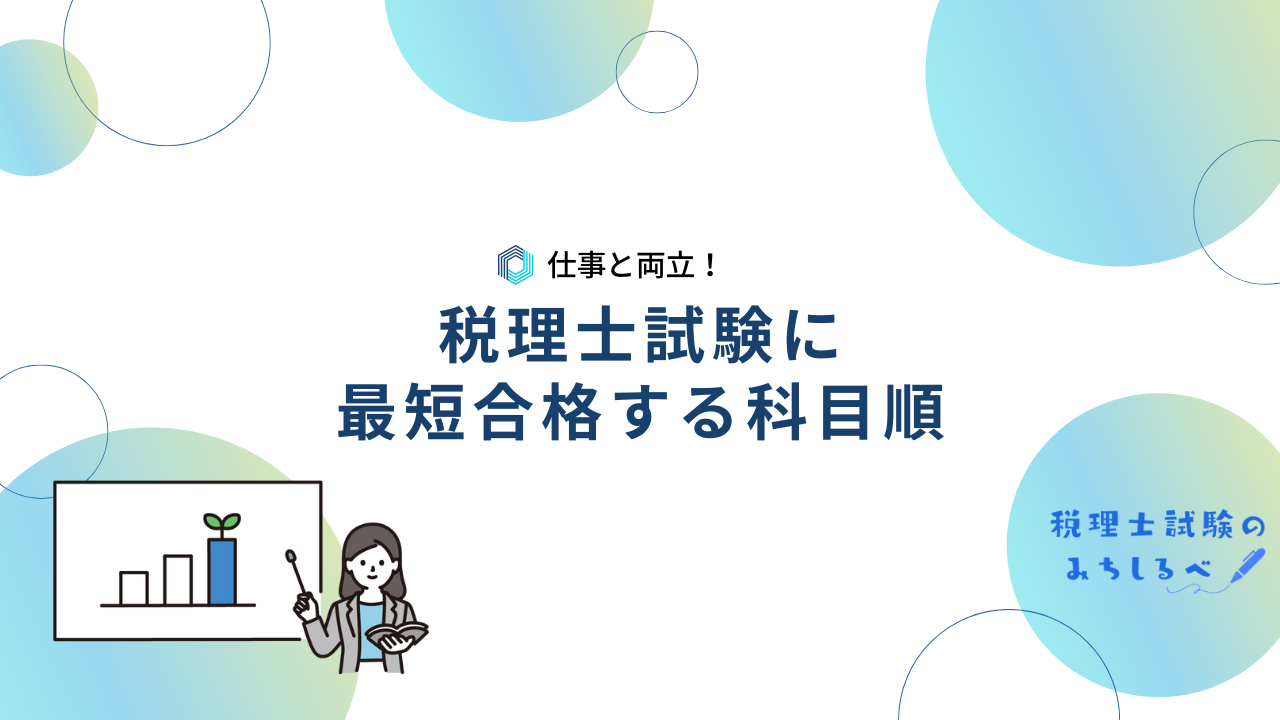
- 仕事が忙しく、十分な勉強時間を確保できない…
- 税理士試験をどの科目から受験するべきか迷っている
- 長期戦になりがちな税理士試験でモチベーションを維持できるか不安
このような悩みを解決します。仕事をしながらでも効率的に合格を目指したい方は多いですが、科目選択の間違いや、学習計画の組み立て方を誤ってしまうと、時間も気力も大きく消耗してしまいます。
多くの方が言うのは、「科目順」と「勉強時間の確保」に大きな課題を抱えているということです。しかし、適切な科目の優先順位と学習スケジュールを設定すれば、限られた時間のなかでも着実に合格を勝ち取ることが可能です。
この記事を読めば、あなたに合った最短合格の科目順が見えてくるだけでなく、勉強を長期的に続けるためのモチベーション維持のポイントまで理解できるようになります。
ぜひ最後まで読んで、無理なくスムーズに税理士試験合格を勝ち取りましょう!

はじめに:仕事と両立しながら税理士試験に合格するために
社会人受験の現状と課題
仕事と両立しながら税理士試験に挑む人が増えています
近年、税理士試験にチャレンジする社会人の方が増えています。
経理や財務の専門知識を深めたい、キャリアアップを目指したい、将来的に独立開業を視野に入れている──さまざまな理由で、日々の仕事と両立しつつ勉強を続ける方が少なくありません。
社会人が抱える大きなハードル
とはいえ、税理士試験の社会人受験には、いくつか大きなハードルがあります。
- 時間の制約
平日は仕事が優先で、勉強時間を確保するのが難しい。 - 体力・気力の維持
残業や休日出勤などで、心身の疲れが溜まりやすい。 - 科目数の多さ
合格までに5科目をクリアしなければならないため、学習計画が長期にわたりやすい。
このように「仕事・プライベート・試験勉強」の三立が求められるため、事前にしっかりとした学習戦略を立てないと挫折しがちです。
たとえば、会計事務所の勤務経験がない方は実務知識をイメージしづらく、独学で理解に時間がかかるケースがあります。
また、経理や財務の経験があっても、簿記論や財務諸表論以外の税法科目(法人税法や消費税法など)はまったく初めてということもあります。
さらに、残業が多い職場だと、平日にまとまった学習時間を確保するのが難しく、休日は家族や趣味の時間ともバッティングするなど、日々のスケジュール管理が非常にシビアになります。。
科目順を工夫すれば合格スピードを上げられます
しかし、効率的に学習を進めることができれば、社会人受験でも最短ルートで合格を狙うことが可能です。次のステップでは、なぜ“科目順”が重要なのかを掘り下げながら、具体的な対策方法に触れていきます。
なぜ“科目順”が合格スピードに影響するのか
最初に受験すべき科目が最終的な5科目合格を左右する
税理士試験は、簿記論や財務諸表論などの会計科目に加え、法人税法や所得税法などの税法科目を含む5科目を合格する必要があります。
これらの科目にはそれぞれの関連性や初学者に向いている科目とそうでない科目があり、最初に受験すべき科目を見極めることで学習効率を大きく高めることが可能です。
難易度や出題範囲の重複が戦略に直結する
- 会計科目を先行して学ぶメリット
簿記論や財務諸表論を学ぶことで、ベースとなる会計知識が身につきます。これにより、法人税法や消費税法を学ぶ際も、仕訳や会計処理がスムーズに理解できるようになります。 - 税法科目の選択順
税法はそれぞれの範囲が非常に広く、難易度も異なります。
実務面を考慮して、法人税法や消費税法を受験する受験生が多いですが、学びやすい科目から着手して合格実績を作っておく方が、時間と精神的余裕の面で有利です。

私が最初に合格した税法科目は、「国税徴収法」です!
受講者20万人超!
科目の相乗効果で効率アップ
たとえば、簿記論と財務諸表論は共通点が多く、同じタイミングで勉強を進めると相乗効果が期待できます。片方で学んだ理論がもう片方の実践問題に生きることがあるため、学習時間を圧縮できます。また、ある程度会計の基礎が固まった段階で税法科目に移行すれば、仕訳に関する混乱が少なくなり、理解が深まりやすいです。
科目順を意識するだけで学習効率が劇的に変わる
要するに、闇雲に学習を始めるよりも、科目間の関連性を理解しておくことで、同じ勉強時間でも得られる知識が何倍にもなります。限られた時間で学習しなければならない社会人だからこそ、この科目順の選択が合否を分ける重要なポイントになります。
税理士試験の基本構造をおさらい
税理士試験とは?
まずは、税理士試験について簡単に整理します。
税理士試験は、税務に関する専門的な知識を問う国家試験です。
税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼に応え、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命としています。
国税庁_税理士制度
https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishiseido/seido2.htm#a-1
税理士試験を合格することで、税務に関する専門家としての資格を得ることができますが、
その試験の難易度は、みなさんご存じのとおり相当難しく、簡単には受からないのが実情です。
税理士試験をパスするためには、会計学に属する科目(簿記論及び財務諸表論)の2科目と税法に属する科目(所得税法、法人税法、相続税法、消費税法又は酒税法、国税徴収法、住民税又は事業税、固定資産税)のうち受験者の選択する3科目(所得税法又は法人税法のいずれか1科目は必ず選択しなければなりません。)に合格する必要があります。
科目合格制=メリットばかりではない
税理士試験は科目合格制をとっており、受験者は一度に5科目を受験する必要はなく、1科目ずつ受験してもよいことになっています。
最終的には、5科目すべてを合格しなければならないため、税理士試験は他の資格試験に比べても受験期間が長期化しやすく、社会人が仕事と両立しながら5科目合格を目指すにはしっかりとした戦略が不可欠です。
まずはそれぞれの科目の特徴を理解することが重要です。会計科目と税法科目では学習の進め方も異なり、難易度や合格率、学習範囲にばらつきがあります。
ご自身の目標やスケジュールに合わせて、最適な受験順と学習計画を組み立てていきましょう。
最短合格を狙う!科目順を決める3つのポイント
ここでは、仕事と両立しながらもスピーディーに合格を目指すための「科目順」の考え方を3つの視点から解説します。
① 業務や実務経験とのシナジー
現在の仕事や実務経験と密接に関係する科目からスタートすると、勉強と仕事の両方で知識が活かせるため、学習効率が上がります。
たとえば、経理や財務に携わっている方なら、「簿記論」や「財務諸表論」を学ぶことで日々の業務で使う知識に深みがでて、税理士試験の学習が役立っているという実感が湧き、モチベーションが高まることが考えられます。
また、実務で培った経験を試験の問題演習などに当てはめやすくなり、理解が深まるメリットもあります。
逆に、税務的な処理に携わる部署であれば、法人税法や消費税法などから着手するのも手です。
・Point
日々の仕事とリンクしやすい科目から始めることで「学んだらすぐ使える」実感が得やすく、長期戦で大切なモチベーションを維持しやすくなります。実務と学習の好循環をつくり出すことで、勉強時間が限られている社会人の方でも最短合格が狙いやすくなるでしょう。
② 会計科目はまとめて受験する
一部の科目同士は内容が重なっていたり、共通する論点があるので、関連性を意識しながら受験順を組み立てると学習効率が高まります。
たとえば「簿記論」と「財務諸表論」は、どちらも会計処理や会計基準に関する知識がメインとなります。「簿記論」をしっかり習得すると、「財務諸表論」の勉強を始めた際に、計算問題で迷うことが少なくなります。
つまり、学習内容を効率よく“使い回せる”わけです。
- 簿記論 → 財務諸表論:どちらも会計理論や仕訳・勘定科目の理解がベースになります。簿記論で身につけた計算力や仕訳知識が財務諸表論の試験勉強に直結し、負担を軽減できます。
・Point
相性の良い科目をペアリングして受験順を組むと、単純に2科目分の学習時間が大幅に減るわけではありませんが、重複する知識を活かせるため、結果的に合格までの時間を短縮できます。中長期の勉強計画を立てる際は、「どの科目がどの科目とつながるのか」を意識してみてください。
③ 勉強開始の時期も考慮する
税理士試験は、毎年8月に実施されますが、勉強開始がちょうど1年前とは限りません。
自分の勉強の開始時期も踏まえて、受験科目の勉強ボリュームを考慮して科目を選択していくと、効率的なスタートが切れます。
税理士試験の科目は「簿記論」「財務諸表論」「法人税法」などは、非常にボリュームが多く、覚えるべき理論が多いため、現実的に、丸1年間の勉強期間が必要となってきます。
例えば、勉強開始が3月となると試験まで5カ月しかなく、これらの科目の合格は難しいです。
かといって、今回の受験を見送るという選択肢も、1年に一回しかない受験機会を無駄にするということであり、非常に勿体ないとわたしは感じます。
・Example(具体例)
- 勉強開始が年内の方(9月~12月頃):「簿記論」と「財務諸表論」をまとめて受験する。
- 勉強開始が年明けの方(翌1月~3月頃):
比較的ボリュームの少ない「消費税法」や「国税徴収法」から受験する。
・Point
まずは市販テキストを軽く確認し、難易度と自分の“好み”や“得意分野”をしっかり見極めましょう。

私は「国税徴収法」から受験しました!(結構珍しいパターンかも?)
受講者20万人超!
おすすめの科目順パターンとその理由
簿財受験からの王道パターンがやはりおすすめ
税理士試験に最短合格するには、簿記論・財務諸表論 →(選択税法科目)の順で進める“王道パターン”がやはり効果的と感じます。
なぜなら、簿記論と財務諸表論は基本となる会計分野であり、相互に関連性が高いため同時受験や短期間での連続受験が合格率アップにつながりやすいからです。ここで土台を固めておけば、後の税法科目の理解もスムーズに進み、忙しい社会人でも効率的に合格を狙えます。
・Reason
- 会計の基礎をまとめて学べる
簿記論と財務諸表論は、経理や会計の基礎知識を扱う科目です。これらを同時、または連続して学ぶことで、仕訳や財務諸表の全体像を効率的に理解できます。 - 相互に関連性が高く学習効果が倍増
簿記論は仕訳の理論や実務処理が中心ですが、それらの結果が最終的に財務諸表論で扱う貸借対照表(B/S)や損益計算書(P/L)に反映されます。両科目を同じ時期に学ぶと、「この仕訳がどのように財務諸表に影響するのか」がつながりやすく、理解度が深まりやすいです。 - 早期合格でモチベーションが保てる
会計2科目の合格を早めに確保すると、「試験のコア部分をクリアした」という自信が生まれます。税理士試験は長期戦になることが多いですが、ここで成功体験を積むと、後続の税法科目へのモチベーションを高く維持しやすくなります。

会計科目2科目を1年でパスした人は、やはり5科目合格も短期化する傾向にあると感じます!
もしあなたが忙しい社会人で、「一番最初にどの科目から始めればいいのか…」と悩まれているなら、この王道パターンで学習を組み立てることをおすすめします。まずは簿記論・財務諸表論で基礎をしっかり固め、早期合格を目指しましょう。その成功体験が、後の税法科目(法人税法・消費税法・相続税法など)への学習を加速させてくれます。
勉強開始が年明けの人は、小ボリュームの税法から攻めるのも手
前述の通り、簿記論・財務諸表論 →(選択税法科目)の順で進める“王道パターン”をおススメしますが、勉強開始の時期が年明けと比較的遅い人にとっては、税法から受けるのも手です。
なぜなら、簿記論と財務諸表論、法人税法は試験範囲が非常に広く、年明けからの勉強では合格ラインに持っていくことが難しいからです。
ここであえて勉強時間が比較的少なくて済む消費税法や国税徴収法のような税法科目から受験することには、下記のようなメリットがあります。
・メリット
- 難易度の高い税法から合格することで気持ちが楽になる
消費税法や国税徴収法は勉強ボリュームが比較的少ないとはいえ、難易度は非常に高いものとなっています。これらを先に合格しておくことで、自分でも5科目合格できるんじゃないか?という気持ちが芽生えてきます。 - 早期合格でモチベーションが保てる
時間がないからと言って1年受験を見送ると合格までの年数はその分長くなります。税理士試験はただでさえ長期戦の資格試験になります。1科目でも先んじて受かっておくことは、自信にもなり、モチベーションを高く維持しやすくなります。
私自身、合格の順番は、「国税徴収法」⇒「簿記論・財務諸表論・消費税法」⇒「法人税法」なので、受験順は王道パターンに縛られず、柔軟に考えて検討してみてほしいと思います。
仕事と両立できる学習スケジュールの組み立て方
プライベートと勉強の両立が社会人最大の課題
働きながら税理士試験に合格するためには、限られた時間をいかに有効活用できるかがカギです。本章では、平日夜や週末の使い方、スキマ時間の活用法など、社会人が無理なく続けられる学習スケジュールの組み立て方をご紹介します。
平日夜と週末を活用する勉強時間の確保術
多くの受験生は、仕事の忙しさに押されて「勉強時間が取れない」という悩みを抱えています。しかし、実際はちょっとした工夫を積み重ねることで、平日夜や週末、スキマ時間などの“隙間”を学習に充てることができます。これらを駆使すれば、勉強量を増やすと同時にモチベーションを保つことが可能です。
仕事と両立する受験生の多くが取り入れているのが、「平日×少しずつ+週末×まとめ勉強」のハイブリッド型スケジュールです。以下のように、時間帯を区切って学習計画を立てると、無理なく勉強を続けられます。
| 時間帯 | 活用方法 | メリット |
|---|---|---|
| 平日夜 | 夕食後の1〜2時間を集中勉強に充てる | 疲れが出る前に“最優先タスク”として学習できる |
| 週末午前 | 朝のうちに3〜4時間を確保する | 頭が冴えている時間を使うので効率が高い |
| 週末午後 | 午前で疲れを感じたら午後は復習中心に | 集中力の波に合わせたバランス学習ができる |
- 平日夜のポイント
- 仕事から帰宅したら“すぐ勉強モード”に切り替える。夕食後、スマホやテレビから離れ、集中できる時間を確保する。
- 勉強時間を明確に区切る(例:20:00〜22:00)ことで、ダラダラしにくくなる。
- 週末のポイント
- 朝型の方は午前中にメイン科目を集中して学習。午後は疲労が溜まりやすいので、暗記や復習に充てるなど強弱をつける。
- 家族の予定やプライベートとのバランスを考慮しながら、あらかじめ“固定スケジュール”を組むことで確実に学習時間を確保する。
スキマ時間に効果を上げる学習テクニック
税理士試験のようにボリュームがある内容を身につけるには、短時間でも継続的に学習する工夫が必要です。以下の方法を取り入れてみてください。
- 理論暗記音声の活用
- 理論暗記音声を利用し、通勤・通学中などの移動時間に理論暗記を進める。
- 理論科目や用語の暗記には最適。
- デジタル教材のフル活用
- オンライン講義や過去問アプリなど、スマホで学習できる環境を整える。
- ちょっとした待ち時間でも動画講義を1テーマ消化できる。
- ポモドーロ・テクニック
- 「25分間勉強+5分間休憩」を1サイクルとして繰り返す方法。短い集中を重ねるので、疲れず学習リズムをキープできる。
- スキマ時間や出先での5〜10分を「休憩時間」に当てはめるなど、柔軟に応用が可能。
仕事と両立して税理士試験に合格するには、平日夜や週末の“まとまった時間”と通勤・休憩などの“スキマ時間”の両方を意識して効率的に使うことが重要です。学習スケジュールは自分の生活リズムに合わせて細かく調整し、無理なく続けられる仕組みを作りましょう。そうすることで、忙しい社会人でも合格に一歩ずつ近づくことができます。
まとめ:自分に合った科目順で最短ルートを目指そう
科目順の決定が合格への近道
税理士試験において最短合格を目指すには、「自分に合った科目順」を決めることが最も大切です。なぜなら、科目選択や受験順によって学習効率やモチベーションが大きく左右されるからです。
税理士試験は5科目合格が必要であり、一度にすべての科目を受験するケースは少なく、多くの方が複数年かけて合格を目指します。もし相性や難易度を考えずに科目を選んでしまうと、以下のようなリスクが高まります。
- 仕事との両立が困難になる
業務で忙しい時期と難易度の高い科目の学習が重なると、勉強時間が十分確保できず、不合格やモチベーション低下につながりやすいです。 - 合格までの期間が長期化
間違った順番で進めた結果、同じ科目を何度も受験する事態となり、受験期間が長引く可能性があります。
実際に、科目順を工夫したことで私自身も3年で5科目と短期間で合格することができました。
最終的には、自分自身の「得意・不得意」「仕事との兼ね合い」を総合的に見極めて科目順を決定することが、最短合格への近道となります。この記事を参考に、まずはご自身の強み・弱みを整理し、ムリのない計画を立ててみましょう。そうすることで、着実に一歩ずつ合格に近づくことができ、将来的にはあなたが理想とするキャリアや働き方を実現できるはずです。
「最も良い税理士講座を、革新的な低価格で」を目指した新しい税理士講座です。
他社の税理士講座ではできない圧倒的な低価格を実現した「最高に合格しやすい通信講座」です。
まずは自分の勉強スタイルにあうか、無料体験から!